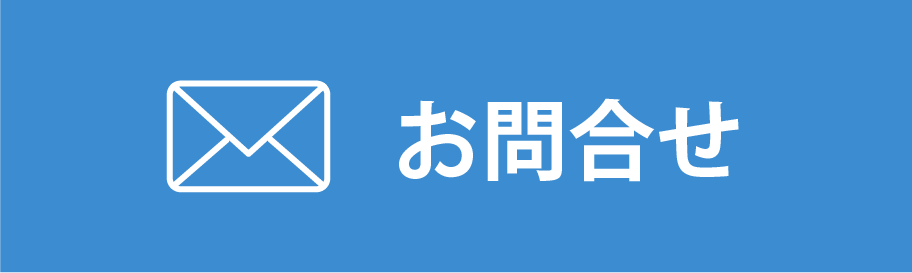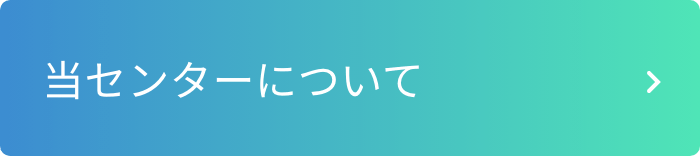周産期(産科)フェロー
募集要項
周産期専門医(母体・胎児専門医)養成コースのお知らせ
母体・胎児専門医は、産婦人科の4つのサブスペシャリティ領域の1つを担う専門医であり、合併症のある妊産婦や胎児に対して専門的な管理ができる知識と技能を備えた臨床医に対して日本周産期・新生児医学会が認定します。当センターは、学会から認定を受けた母体・胎児専門医取得のための研修基幹施設であり、これまでに多くの母体・胎児専門医を輩出しています。
当センターは全国に先駆けて1981年に設立された周産期母子医療センターであり、大阪府における周産期医療の中核施設として、30年以上にわたってハイリスクの妊産婦や胎児の診療を担ってきました。また、OGCS(産婦人科診療相互援助システム)の基幹病院として、大阪府内さらには近畿全域からの母体搬送・産科救急の受け入れやコーディネートに24時間対応しています。母体および胎児への集中的な管理のために母体胎児集中治療管理室(MFICU)を9床運用し、集学的な管理のために新生児科、母性内科、麻酔科、さらに小児外科、循環器内科などの小児系診療科と緊密に連携をとっています。また、西日本全域から対象症例を受け入れ、胎児治療を行っています。一方、診療対象はハイリスク症例に限っておらず、特にリスクを持たない妊産婦の妊娠・分娩管理も数多く手がけています。(PDF参照)
当センターでは母体・胎児専門医を目指す若手医師の研修を受け入れています。当センターの診療環境では、専門医を目指す医師にとって十分な臨床経験を積むことができます。また、それぞれに得意分野を持った指導医層が、充実した研修になるように指導します。周産期医療を究めたいという熱意をもった医師からの連絡を待っています。
| 連絡先:産科医局 | obst(a)wch.opho.jp (a)を@に変換してください |
|---|
フェローメッセージ
| 母子医療センターでの研修を選んだ理由 | サブスペシャリティとして周産期を専門的に勉強したいと思ったからです。 |
|---|---|
| 母子医療センターでの研修のよいところ | ハイリスクの症例が多く、上級医が熱心に指導してくれます。各診療科との密な連携と協力により、難しい症例の管理が可能であったりと非常に勉強になります。 |
| 将来のビジョン |
2年間の研修を終えた後、地域周産期に貢献したいと思います。 |
| ひとこと | 珍しい症例や難しい症例に出会った時の向き合い方や日々の診療に対する考え方が変わりました。忙しい日もありますが有意義な研修を送ることができます。 |
募集要項
| 対象 | 日本産科婦人科学会産婦人科専門医(取得予定を含む)で卒後15年程度までの方 |
|---|---|
| 期間 | 6か月~3年間、日本周産期・新生児医学会母体・胎児専門医取得の年まで |
| 内容 |
産科診療全般を行いながら、希望した領域での重点的修練も可能である(例、胎児外来を担当など)。希望に応じてNICUでの短期研修も選択可能である。学会発表や論文執筆も適宜行う。 |
| 身分 |
非常勤医師(状況により、常勤採用の可能性あり) |
| 報酬額 | 要相談 |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険適用 |
| 募集人数 |
|
| 選考日時 |
随時 |
| 選考基準 |
|
| 応募締め切り |
|
メニュー
- 専攻医・研修医・医師
- 医師
- 小児科専攻医
- 看護師
- 看護師・助産師
- コメディカル
- 医療技術職員
- 研究職
- 流動研究員・研究補助員
- その他
- 事務・その他職種
- 現在募集中の採用情報
- お問合せ
- エントリーフォーム