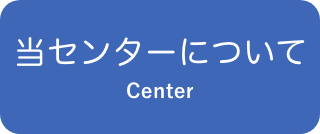総長からのごあいさつ
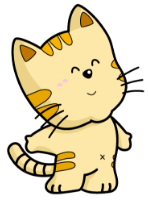
総長からのごあいさつ


はじめに
当センターは、周産期医療の専門的な基幹施設として、地域の医療機関では対応が困難な妊産婦や低出生体重児・新生児に対して高度・専門医療を行うため、1981年に診療を開始しました。1991年には、小児医療部門を開設し、小児の高度・先進的な医療も提供してきました。
最近は、ローリスクな分娩も積極的に受け入れています。また、小児救急を含め、幅広い小児の内科・外科的疾患患者も積極的に受け入れています。
当センターは、1999年に大阪府で最初の総合周産期母子医療センター、2018年に小児救命救急センター、2020年には二次救急告示医療機関、2022年に小児中核病院に指定され、周産期・小児すべての分野において大阪府の中核的施設として認定されています。2022年には泉州の小児救急輪番の1つに加わり、一部ですが小児1次救急も担っています。
小児部門開始と同じ1991年には研究所を開設し、病院と一体となって周産期・小児分野の希少・難治性疾患のゲノム解析・病態解明や診断・治療法の開発に取り組むとともに、学術的にも大きな成果を挙げています。
母子保健事業は開設以来の当センターの根幹です。保健師による現場での保健相談・指導を行うとともに、環境省のエコチル調査、大阪府のにんしんSOS、妊産婦こころの相談センターなどの受託事業があります。今後、この分野での研究成果を挙げるとともに、大阪府の母子保健で指導的な役割を果たしていきたいと考えています。
2024年度の取り組み
本年度は、2024年4月から開始された「医師の働き方改革」への対応に大きな労力を要しました。当センターは周産期医療や小児救急を含む小児医療という救急や宿日直を要する部門が多いため、A水準に収まる診療科が限られ、B, C水準を申請せざるを得ない診療科が多くなりました。さらに、産科をはじめ宿直許可をとらざるを得ない診療科も多く、地域の労基署とのやり取りも大きな事務量でしたが、かなり多くの宿直許可を取得することはできました。
2024年も当センターの最重要課題は、病院の建て替えに向けて前進することでした。2023年4月からの基本設計はセンター職員の協力で順調に完成しました。建替え費用が当初の計画とはかけ離れた高額な見積もりとなり、何度か計画の見直しをせざるを得ない事態となりました。これに対しては、府立病院機構本部はもとより、知事をはじめ大阪府の理解と大きな支援をいただきました。残念ながら、入札希望調査で希望する建設会社がないという結果に終わり、入札不調となりました。ここ1年は当センターと同規模の公的病院の建替えは、確認できた中ではすべて入札不調に終わっていますが、当センターも例外ではありませんでした。この背景としては、第一に著しい建築費の高騰ですが、現場の作業員、とくに設備関係の人員の不足も指摘されています。今後は、まず入札不調の背景を詳しく解析するとともに、その結果も踏まえて、機構本部や大阪府と協議しながら、建替え計画を粛々と進めたいと思います。
大阪母子医療センターの診療
- 総合周産期母子医療センター
府内随一の総合周産期母子医療センターとして、他の医療機関では受け入れ困難なハイリスク妊産婦、胎児や超低出生体重児の治療を行っています。同時にローリスクのお産を積極的に受け入れています。
大阪府のOGCS(産婦人科診療相互援助システム)、NMCS(新生児診療相互援助システム)の中核的役割を担い、母体緊急搬送、新生児搬送例を積極的に受け入れています
「無痛分娩」を積極的に実施しています。麻酔医がすべて管理することで万全な安全体制をとっていますので、安心して受けていただけます。実施数も大きく増えて、現在、通常分娩の5割を越える方が無痛分娩で快適でしかも安全なお産をされています。 - 小児医療―希少・難治例を含む幅広い小児疾患に高度な医療を提供
小児医療の基幹施設として、小児がんを含む難治性の内科的疾患や先天性心疾患などの新生児・小児の外科的疾患に対する高度専門医療を提供しています。麻酔科・集中治療科も充実し、術中・術後の管理が難しい乳幼児に対する手術も数多く行っています。
同時に、幅広い小児の内科・外科的疾患患者も積極的に受け入れています。 - 多職種によるチーム医療の充実・長期フォロー、在宅医療の促進
高度専門医療を提供するにあたって、医師・看護師・医療技術職などが一体となってチーム医療を推進しています。主疾病の治療だけでなく、合併症や心の問題への適切な対応や家族への支援などのため、心理士やホスピタル・プレイ士など多くの専門職種も協働して、こども達の成長に合わせた関わりを提供しています。
病院内の環境整備を行うとともに、ボランティアによる託児、ファミリーハウスの設置、さらにはこどもが主体的に治療に取り組めるよう保育士などの配置を行い、病気の治療はもちろん健やかな発達を支援する体制を整え、実践しています。
急性期治療終了後の患者さんの生活の質改善のため、地域関係機関との連携のもとで、保健師、ケースワーカーや看護師などによるフォローアップも行っています。特に低出生体重児の発達フォロー、性分化疾患や小児がんの患者さんの晩期合併症としての思春期以降の心の問題や生殖機能・妊孕性のフォローに力を入れています。
在宅医療への移行も、地域の関係機関のご協力をいただきながら積極的に進めています。また、大阪府の事業も受け入れ、移行期医療にも力を入れています。
人材育成
小児科研修では専攻医の基幹施設となるとともに、多くの診療科が大学病院などの研修連携施設となっています。産科シニアフェロー制度を設置し、専門医の育成を行っています。また、次世代リーダーの人材育成を行う環境整備を行い、継続して高度な医療が提供できる体制を整備します。
看護部門やコメディカル部門でも多くの研修生・実習生を受け入れ人材育成に大きく貢献しています。
研究所でも当センター医師や大阪大学医学部などの大学院生を積極的に受け入れ、研究者を育成しています。
最後に
当センターは、高度専門医療・研究をさらに推進し、未来を担うこどもたちが病気に打ち勝ち、健やかな成長を遂げて、こども達とご家族が「勇気、夢そして笑顔」を持てるよう、患者さんを中心とした医療を提供します。
また、若い医師・看護師・コメディカルなどの皆様が当センターで勤務したい、研修したいと憧れて頂けるよう診療、研究、人材育成など、すべての面で日本の周産期、小児医療をリードする病院を目指します。
(2025年4月)
地方独立行政法人大阪府立病院機構
大阪母子医療センター
総長 倉智 博久
センター概要
- センター概要
- センターの組織
- 総長からのごあいさつ
- 基本理念
- 沿革・設置目的
- 患者さんの権利について
- 子ども憲章
- 認定・資格
- 厚生労働大臣の定める掲示事項
- センターパンフレット
- お問合せ・サイトについて
施設紹介
組織紹介
センターの取組み